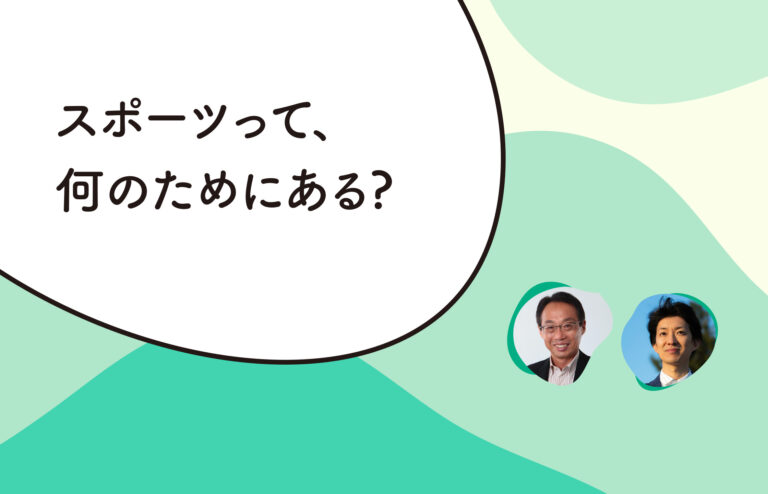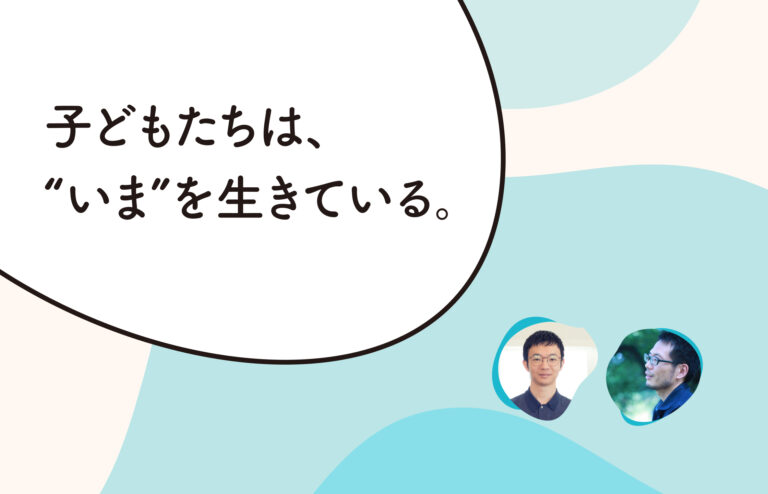言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性 こここインタビュー vol.32
自分の身体を使って、誰かと一緒に動いたり、呼吸を合わせたり。時に言葉にしがたい、人と人との“交流”が起こるのは、ダンスや演劇、音楽など「パフォーミングアーツ」の大きな魅力だ。
一方で、絵画や彫刻のようにかたちが残らず、不確かさが伴う点は、表現活動として取り組むときのハードルにもなっている。芸術文化活動が全国的に広がりを見せている福祉施設でも、美術表現に比べ、身体を使った実践はまだまだ少ない。
こうした状況の中で、〈厚生労働省〉が推進する「障害者芸術文化活動普及支援事業」では、美術分野での表現活動のみならず、近年はパフォーミングアーツをテーマに幅広く実践に取り組む事例も増えている。自由な身体表現の活動の中には、そこに潜む「わからなさ」を大切なものと受け止め、私たちの既存の価値観すら変えていくような実践もある。
今回、同事業の連携事務局を担当している〈NPO法人 アートNPOリンク〉の田中真実さんと、児童福祉施設でのアーティスト・ワークショップのコーディネート経験が豊富な〈NPO法人芸術家と子どもたち〉の中西麻友さん、演劇ライターの鈴木励滋さんをお呼びし、多角的な観点からパフォーミングアーツの可能性や、普及のためにできることを考えてみた。

関係性や価値観を解きほぐす、“身体”の表現活動
パフォーミングアーツとは、さまざまな空間で肉体を使って表現を行う芸術の総称だ。具体的には演劇、ダンス、音楽、歌舞伎、ミュージカル、朗読などが含まれている。例えば、ダンスならば、目の前に人が感じられている状況で自らの身体そのものを使って表現することに、演劇ならば、舞台に関わる全員で共通のフィクションを作り上げていくことなどに一つ大きな魅力がある。
中西さんが事務局長を務める〈芸術家と子どもたち〉では、コンテンポラリーダンス(表現方法に決まりがない自由なダンス)や音楽、美術、演劇といったジャンルの現代アーティストと子どもたちが、学校や児童福祉施設、少年院や小児病棟などで出会う場をつくる活動を約24年間続けてきた。長年ワークショップのコーディネートをするなかで見つけたその魅力を、中西さんは「バーチャルではない現実で、互いの身体をちゃんと感じられること」と表現する。
中西麻友(以下、中西) 他者を感じることは、絵画や彫刻などの作品をつくる美術や、音楽でもできます。ただ、色々な特性のある子どもたちと関わるうえで、道具や言葉を挟むともどかしく感じることもある。パフォーミングアーツでは、自分の身体にとって本当に“気持ちいい”ことか、そうでないかを読み取っていきます。もどかしさを超えてわかろうとするときに発揮される、身体の力はすごいなと感じています。

〈芸術家と子どもたち〉の活動においては、アーティストをゲストに呼んで行われる「ワークショップ」が一つの形となる。同団体ではその意義を、子どもたちにとっては「潜在的な力を存分に発揮し伸ばす機会」、 アーティストにとっては「子どもたちと関わり新たな表現を探る機会」と捉え、活動を重ねてきた。予め用意された正解やゴールを目指すのではなく、子どもと大人が互いに気づきを共有し、作用し合うような出会いの場になることを大切にしている。
同様に、ワークショップの本質にある「参加型であること」「体験型であること」「双方向性があること」の重要性を指摘するのが、演劇ライターの鈴木さんだ。文化芸術のフィールドに詳しい鈴木さんは、2024年3月まで生活介護事業所〈カプカプ〉の所長を、現在は生活介護事業所〈ミコミコカンパニー〉でサービス管理責任者を務めており、障害福祉の現場で長年活動してきた人物でもある。
東日本大震災とほぼ同時期に体奏家の新井英夫さん・画家のミロコマチコさんと出会い、2人とのワークショップを〈カプカプ〉で始めたのをきっかけに活動を広げ、2021年には〈カプカプ〉のある横浜市旭区の福祉施設6か所を巻き込みながら「障害福祉施設におけるアーティストとのワークショップ定着事業」を開始。その後も形を変えて事業を継続させながら、他の福祉施設へのワークショップのコーディネートにも勤しんでいる。
鈴木励滋(以下、鈴木) 現在の福祉制度の中では、福祉施設職員の感覚も、既存の社会に適応させていく「訓練」的な発想になりがちです。ワークショップをやってみることでスタッフの反応が変わっていくのは、施設のメンバーにとってもプラスの影響が非常に大きいと思いました。
アーティストとともに時間を過ごすことで、障害のある人が表現手段を獲得するだけでなく、その行動を「指導の対象」でなく「表現」として受け止められる力や、スタッフの「おもしろがる」力も育まれていくと鈴木さん。実際に鈴木さんの仕掛けるさまざまなワークショップでは、従来のルールや思考から離れ、関係性や価値観を解きほぐす時間が流れていく。

言葉が「理解する」ツールなら、身体は「つながる」ツール
もちろんパフォーミングアーツには、予め用意されたセリフを読む演劇や、決まった振り付けを踊るダンスもある。しかしそれだけではなく、中西さんと鈴木さんの語りからわかるように、もっと自由な形で取り組めるジャンルだ。なのに、なぜ今も福祉的な現場で、美術活動に比べ身体表現活動は普及しづらい(※注)のだろうか。
※注:『2023年度障害者芸術文化活動普及支援事業報告書』では、美術企画への出展者は9700人、舞台芸術企画への出演者は1255人(p138)
演劇の場合は「良い声で演じるもの」といった旧来のイメージや、発表する際に「高い再現性」を求められるのではないかという不安が、敬遠される理由になりやすいと鈴木さんは指摘。中西さんも、他のアートとダンスの違いに触れながら同意する。
中西 美術なら「この作品が完成しました」、音楽なら「この曲が弾けるようになりました」と、成果がわかりやすいんですよね。とくにコンテンポラリーダンスのように言葉を発しないものは、見ている側が「よくわからない」で終わってしまうのでは……と施設職員や先生が、成果をどう評価していいかわかりづらいことに不安になりがちなのかもしれません。

確かに私たちの多くは、作品を鑑賞する際の方法として、背景や意図など言葉を使って「わかろう」とする。ダンサーの踊りの中には、それがしづらいものも少なくない。それでも、コンテンポラリーダンスを目の前にした子どもたちは「大人がわからないと思うものからでも、なにかを感じ取ってくれる」と中西さんは話す。
中西 もし「わからない」と思ったとしても、アートに正解はないので、自分で考えられる余地があります。そして「別にすべてをわかろうとしなくてもいいんだ」ということも肌で感じられる。背景や意図にたどり着くことよりも、生の人間の身体が今まさにそこで動いている、そのエネルギーや衝撃を感じることだけで充分なのではないかと、子どもたちを見ていて思いますね。
言葉で理解できていない状態だとしても、間違いなくなにかとの交流が起こっている。そんな中西さんの話を受け、鈴木さんも自らのダンスとの衝撃的な出会いに触れる。
鈴木 全くわからないし悲しくもない作品を観て、僕、泣いたことがあるんですよ。それまで、世界のことって自分の中で言葉で考えて、ある程度は整理できると思っていたから、どういうことなのか不思議でした。でもそこから、僕は演劇でもまさに、「言葉」や「意味」を追わなくてもいい作品のほうがどんどん好きになっていきました。

アートにおける「わからなさ」の肯定は、芸術分野だけでなく、言葉でのコミュニケーションが得意でない人もいる福祉分野において「希望である」という鈴木さん。そこに身体があって、なんだか言葉にしがたいまま揺さぶられる——そんな「人の存在そのもの」を肯定していくような表現のあり方に、中西さんも賛同する。
中西 自分の気持ちを全部正しく言語化することは、本来大人でも難しいですよね。なのに、障害のある子を含め子どもの気持ちを、先生や保護者である大人はやっぱり理解したくて「言葉」を使ってしまう。それを「言葉」じゃなく「身体」でキャッチしようと試みるのが、ダンサーのようなアーティストなんだと思うんです。
言葉が「理解する」ツールなのだとしたら、身体は「つながる」ツール。アーティストがワークショップで参加者と楽しそうにつながるのを見るうちに、教師や福祉施設の職員も、言葉で理解できなかったことを感覚的に受け取れる瞬間が訪れる。
田中真実(以下、田中) 普段、福祉施設で働いている方々も、一見外からはわからない障害のある人の行動を「どんな意味があるのだろうか」と捉えて、支援していると思うんです。実はそのことと、アーティストが誰かと向き合い、その人を知っていく過程は、とても似ている気がしています。
こう話すのは、「障害者芸術文化活動普及支援事業」の連携事務局を担当している、〈アートNPOリンク〉スタッフの田中さん。アーティストと福祉施設をつなげる存在として、現場の声もよく耳にしてきた。

田中 福祉領域で取り組むパフォーミングアーツでは、中西さんと鈴木さんがおっしゃるように「理解しきれないことへの寛容さ」が魅力になるケースも多いと思うんです。ただ同時に、知らないこと、なにかに揺さぶられることには怖さもある。それを乗り越えて「わからなさ」と向き合うためにも、丁寧に知り合っていけるプロセスが重要ではないでしょうか。
たまたま人生がすれ違って、瞬間的な“交換”が起きる
3人が挙げる「わからなさ」。その言葉にしがたい魅力をどうにか伝えることができれば、表現活動はさらに幅広く、多様になっていくのではないか。だからこそ、それを全国規模で推し進める手段としての障害者芸術文化活動普及支援事業には期待も大きい。
この事業は、全国に実施主体である「障害者芸術文化活動支援センター」(以下:支援センター)などを設置して、アート活動を導入したい福祉施設や、障害のある人と連携したい文化施設、表現活動をしてみたい障害のある人やその支援者、そしてアーティストなどの協力者からの相談を受け、それぞれをつなぐことで障害のある人の表現活動をサポートする取り組みだ。始まった2017年度、20の都道府県に置かれた支援センターの数は、2024年度は46にまで倍増するなど、支援エリアを広げている。
活動領域も拡大するなかで、近年はパフォーミングアーツの事例も散見されるようになってきた。例えば「山形ビエンナーレ」では、ダンスプログラムの企画に支援センターが参画した。一方で、歩く・たたく・しゃべるといった何気ない「日常のふるまいや関係性」も表現として捉えるような活動が全国各地で注目され始めている。
しかしそれでも、「美術に比べて、パフォーミングアーツの取り組みに関わる人はまだ少ない現状がある」と田中さん。あらためて、なぜ「わからなさ」の魅力を扱うことが難しいのだろうかと考えたときに、福祉の現場そのものが、イレギュラーの発生を避けようとする構造に置かれているのではと投げかける。
田中 福祉や教育の現場では、業務に追われ、忙しい日々を過ごしている状況もあるのではないでしょうか。その中で、一人ひとりの行動や表現に向き合うのが難しいタイミングもあると思うんです。どこまでを良しとできるのか、社会的な規範をどこに置くか、取り組む際に判断が分かれることも多いように感じています。
だからこそ、福祉職や教員が日々支援のよりどころにする社会的規範やルールを、アートが揺さぶっていくことが結果的にあらゆる人を楽にしていくはずだ。生きづらいのはいわゆる制度的な「福祉」が必要とされている人だけではないと、中西さんも出会う子どもたちの様子に触れながら語る。
中西 学校へ行くと、特別支援学級の子だけでなく、通常の学級にいる子どもたちも、周囲の空気を読みすぎて身動きがとれなくなっているように思うんです。誰もが本当は愛されたいのに、それがかなわない。障害のあるなしに関わらず、人はなにかしらの生きづらさを抱えているんじゃないでしょうか。

サポートが必要になるのは障害のある人に限ったことではなく、障害のある子どもとない子どもが交流するワークショップの場をつくったときに、障害のない子どもから「障害のある子どもたちは普段から手厚くサポートを受けられてうらやましい」というような声が実際こぼれることもあったという。障害のある/なしで分けられ、立場の異なる人同士がすれ違う機会が減ってしまう現在の環境では、お互いにどんなところに生きづらさがあるのかわからず、それぞれへの配慮が働きにくい状態に陥ってしまうのかもしれない。
中西さんはそんな子どもたちがまずは互いの存在を認識し、自然な交わりが生まれるような場を、パフォーミングアーツによってデザインしようとしている。
中西 一つのワークショップに居合わせることで、たまたまお互いの人生がシュッとすれ違って、なにか瞬間的な交換が起きる。そんなふうに肩の力を抜いて関わりあえる場が、私たちの人生にもっと存在してもいいんじゃないでしょうか。子どもたちや障害のある人と「支援する/される」という一方的な関係にならないためにも、学校や福祉施設が、もっとアートをうまく使える環境をつくれたらと思っています。
支援センターの役割と、生まれつつある文化施設との連携モデル
現在、障害者芸術文化活動普及支援事業では、全国的に設置された支援センターが「福祉施設や文化施設と連携して」中間支援を行っていくことが、一つの目指す姿として掲げられている。それを代表する事例が、東京都江東区にある文化施設〈ティアラこうとう〉による、障害のある人を対象としたダンスの連続ワークショップ「のはらフル」だ。

公立の文化施設として、障害のある人が主体となって芸術活動に参加できる機会をもっと増やせないか。そんな課題意識を持った〈ティアラこうとう〉から支援センターに相談が寄せられ、障害のある人もない人もダンスが楽しめる場づくりに取り組んでいる。また、ファシリテーター養成講座も同時に行い、表現活動がさらに広がっていくよう種を蒔いていることも特徴だ。
田中 最近の支援センターの事業傾向として、障害のある人だけでなく「みんな地続きにいるんだぞ」と参加者のレンジを広げていこうとする動きも起こっています。〈ティアラこうとう〉の事例でも、「江東区内での活動をさらに発展させていきたい」との声が文化施設や地域の福祉施設からあり、翌年は地元の商店街を舞台にしたイベントを開催しました。約100名のダンサーが地域のお祭りに参加するような、次なる展開も起こりはじめています。
もちろん、〈ティアラこうとう〉のケースのように文化施設からの相談を待つだけが支援センターの役割ではない。支援センターから働きかけ、各エリア内で普及してほしいモデル事業をつくることも重要だ。
鈴木 実は福祉施設の中には、演劇のような活動に興味がありながらも、息を潜めるように働いている人は結構いるんですね。そういう思いのある人は、こういったモデルを参考に施設内で提案して、どんどんやっちゃえばいいと思うんです。そこにいる人たちの視点・観点・感覚がこのような活動を通して変わっていくだけで、どれほどその空間が誰にとっても居心地のよいものになるのか。それを体験するに勝るものはありません。
「百聞は一見に如かず」と、最初の一歩の広がりを重視する鈴木さん。ただ、身体表現は前述の通り「こういうもの」という先入観がハードルになっている場合もある。それをクリアして活動を後押しするためには、支援センターのような中間支援組織の関わりも欠かせない。
鈴木 活動について「こういう意味合いもありますよ」と別の角度から言い換えたり、「こういうことが全国で起こっていますよ」と事例を差し出したりするだけでも、興味を持ってくれた人の背中を一押しできます。相談窓口だけでなく、興味を持ったときにいつでも情報にアクセスできるようにしたり、支援職本人が「ああ、これは絶対うちでもやりたい」って思ってもらえるような参加型企画をしたりと、できることはたくさんあると思いますよ。

鈴木さんの話を受け、田中さんも必要な情報を支援センターが揃えておく重要性を語る。その筆頭として、「地域にいるアーティストの情報」を挙げた。
田中 まだ私たちが見つけられていないだけで、地域で非常にいい活動をしている人やアーティストやファシリテーターが必ずいると思うんです。地域の文化施設や芸術団体などと日々情報共有をしつつ、必要なときにつなげていくのが支援センターの役割の一つだと考えています。
一方で、福祉の現場で表現活動のファシリテーションができる人自体を増やすことも必要になる。地方の文化拠点が中心となり、養成スクールを開校する事例も少しずつ出てきており、鈴木さん自身も横浜でアーティスト向けのファシリテーター養成講座を主催してきた。
鈴木 僕は福祉施設にいる人たちにすごく敬意があるからこそ、彼らと対等な関係を築ける力があるアーティストにこそ携わってほしいんです。個人の表現を突きつめすぎてハラスメント行為をしかねないような人ではなく、互いに試行錯誤しながら一緒に作品を作っていける人がいい。そういう人なら、実はそこまで大がかりなレクチャーをしなくても問題なく場をファシリテートできるんです。
福祉現場にいる支援職の中にも、「こうあるべき」を変えたいと願う人たちはたくさんいる、という鈴木さん。ただそういう人は、今の制度や慣習に疲弊して、辞めてしまうこともあった。ファシリテーターのできるアーティストが育ち、それと各支援センターが連携することによって、そんな人たちが辞めなくてもよい場へと、福祉の現場も変わるはずだ。
「わからなさ」を抱えながら、人として肯定する表現活動を
支援センターが存在することで、パフォーミングアーツの事例やモデルケース、それを担えるアーティストと出会えるようになる。そこから、多くの人が身体的な表現活動の本当の魅力を知る機会も増えていくかもしれない。
「表現とはつまり、その存在を表すこと。見てもらってなんぼです」と鈴木さん。そこで起こる新しい波は、どう広がっていくのだろうか。
鈴木 身体表現のワークショップをすると、そこにいる障害のある人たちはもちろん、施設関係者、さらに地域へと変化が広がっていくような感覚があります。〈カプカプ〉でも、最初は障害のある人との関係をいかによくするか考えているうちに、複数のスタッフとの間に広がっていって、みんなの顔つきが変わったことにご家族も気づいて。そこから徐々に、運営していた喫茶店の常連さんだけでなく、商店街の人々へも認知されるようになっていきました。
施設からスタートした表現活動が、さまざまな人の身体を借りて、徐々にまちへとにじみ出し、社会規範や固定観念、既存の関係性を解きほぐしていく。その証拠に〈カプカプ〉の上に住む住民から、ワークショップに関する騒音の苦情が寄せられたことはなかったそうだ。それを鈴木さんは「面白がっていいんだ、という感覚が周辺へと広まっている」と表す。
鈴木 その意味では、実は美術や演劇というジャンルはあまり関係ないんです。僕が一緒にワークショップを開いているアーティストはみんな、目の前の人との関係性の中で作品を作っていける人。「一人ひとりを肯定してほしい」という考え方を共有できる人たちです。そんなふうに人の存在が認められていく活動として、福祉の中にアートがあってほしいですね。

一人ひとりの存在が「ちゃんと肯定される」こと。それは福祉サービスを利用する当事者や支援職だけに留まらず、コーディネートを受けてワークショップを開くアーティストに対してもあてはまることだと、中西さんも応じる。
中西 私たちはワークショップで「子どもたちに失敗してもいいよ」と言える場を作りたいんです。なのに、その場を構成している大人の一員であるアーティストが「失敗してはいけない」と思ってしまうなら、それは不平等ですよね。もちろん、見守る大人側の懸念もわかります。それでもアーティストが自分で「間違えたな」と思ったら、その場にいる誰かを傷つけたり危ない目に遭わせたりしない範疇でやり直してもいい。子どもも大人も一緒に、試行錯誤を積み重ねる過程の中にこそ、大切なことや面白いことが見つかる気がします。
社会規範を揺さぶる手段でもあるはずのパフォーミングアーツもまた、実践の場では「わからなさ」を怖れる構造にとらわれている面があるのかもしれない。福祉領域に限った話ではないが、企画する側が予定通りに進めることを求めてしまいがちだと、田中さんも指摘する。
田中 本来、何かをするときに、最初からすべて思惑通りうまくいくということはないと思うんです。ときには失敗することがあるかもしれません。でも、見方を変えると失敗も失敗ではなかったかもしれない。さまざまな尺度や考え方があるべきです。起こったことの中で、わからないことをその場にいるみんなで話し合う、そのほうが大切なんですよね。

なにが起こるかわからないことは、単純に怖さが先出つ。わかりやすく成果があったほうが安心できる。しかし、そこにいる人と人とが即興的に織りなすパフォーミングアーツの表現活動は、時として言葉すら簡単に乗り越え、周囲に波及していく。
確かにどうなるかはやってみなければわからないし、同じ結果になるものは一つとしてない。しかし、3人の話を聞く限り、そこにいる人や場を確実に解きほぐすものになっていることが伺える。障害者芸術文化活動普及支援事業のWebサイトに、パフォーミングアーツを含め積み上がっている詳細な活動事例は、それを証明しつつ、さらなる広がりを促すものとも言えるだろう。
「周囲も含め、みんなで『一緒に考えていかない?』と言い合える社会のほうが楽しいんじゃないかと思います」と中西さんは笑う。日常を舞台にこれから少しでも多くの人が踊り、演じ、それを許容する社会が広がっていくことを、同事業の成長とともに楽しみにしたい。
Profile
Profile
Profile
![]()
-
鈴木励滋
生活介護事業所サービス管理責任者/演劇ライター
1973年3月群馬県高崎市生まれ。97年から勤めていた生活介護事業所「カプカプ」を2024年度末に離れて、次の場の準備をしている。演劇ライターとしては、劇団ハイバイ・劇団サンプル・劇団はえぎわのツアーパンフレット、「月刊ローチケ」や「埼玉アーツシアター通信」でのインタビュー記事、演劇誌「紙背」や「東京芸術祭」のウェブサイトに劇評などを書いてきた。「障害×アート」については『生きるための試行 エイブル・アートの実験』(フィルムアート社、2010年)、はじまりの美術館企画展「えらぶん:のこすん:つなげるん」記録集(2018年)などへ寄稿。師匠の栗原彬(政治社会学)との対談が『ソーシャルアート 障害のある人とアートで社会を変える』(学芸出版社、2016年)に掲載されている。2022年からは、長年ともにワークショップを開催してきた体奏家の新井英夫や板坂記代子らと、ファシリテーターやコーディネーターの養成に取り組み、自らもコーディネーターとして、これまで十数ヶ所の障害福祉事業所でアーティストによるワークショップを実施してきている。
Profile
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事
vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」