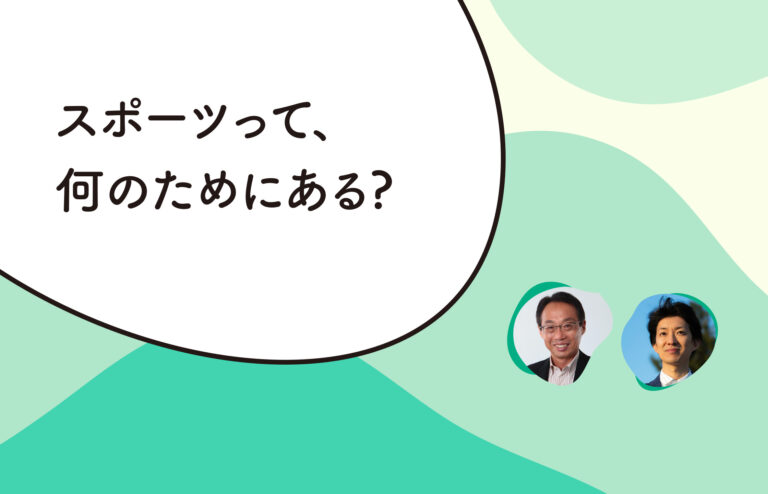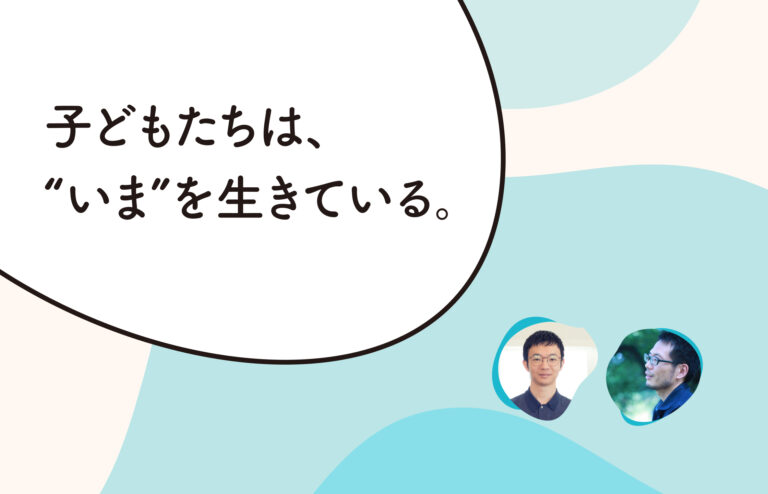地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い こここインタビュー vol.29
思い思いに遊ぶ子どもたちが、テラスや園庭、部屋に散っている。
ここは、0〜6歳の未就学児が通う認定こども園の「のだのこども園」。隣接するのは、千葉県野田市で古くから地域を支えてきた「野田北部幼稚園」の園舎だ。2つの園が、ゆとりのある敷地で森に見守られるように広がっている。

〈学校法人加藤学園〉は、この認定こども園と幼稚園で、現在400人あまりの園児を受け入れている。他に、幼稚園と同じ園舎内で子育て支援広場、そして隣の流山市では「Kanade流山セントラルパーク保育園」を運営。さらには2024年秋、野田市の敷地内に児童発達支援施設も開設する予定だ。
地域の要請にあわせて拡大してきた幼稚園では、現在新園舎への移築・移転が進み、2025年春に認定こども園化(乳児の受け入れ開始)も予定されている。あわせて〈学校法人加藤学園〉から〈学校法人thanka〉へ法人名やロゴサインも刷新、大きな転機を迎えようとしている。
学校法人が、乳幼児の保育や障害福祉までを担うようになった背景には何があるのだろうか? 新たなステートメント「手を繋ぎにいく」を掲げ、地域でどのような存在を目指そうとしているのだろうか? 過去の理念や教育目標を引き継ぎながら、リブランディングに試行錯誤してきた理事長の加藤裕希さん、そのパートナーとして並走してきたデザイナー/アートディレクターの小田雄太さん(COMPOUND inc.)にお話を伺った。

子どもたちの「これやりたい」を保育者が支える園
在園児がパンづくりのワークショップなどにも使うカフェのような地域交流室に荷物を置いて、加藤さんの案内で学園内を巡る。まずは、2019年に開いた定員132名の「のだのこども園」。
風の抜ける日陰のテラスで鉄棒に取り組む子ども、天井から吊るされた遊具にぶら下がって身体をのびのびと動かす子ども。上履きを履いている子も、履いていない子もいるようだ。


部屋の中には、両手いっぱいに絵の具にまみれた子。外の園庭を見渡せば、植物に水をやっている子、園庭の小山を駆けのぼる子。



「外から見ると、カオス感あるでしょう」。加藤さんはそう表現するが、なんだか違うようにも思える。子どもたちは、ただやんちゃに過ごしているだけではない。自由は与えられているが、放任されているのでもない。カオスでありながら、有機的に繋がり合っているようにも思う。その不思議な風景に、興味を惹かれた。
園舎や園庭があるのは、もともと、加藤さんの祖母の代から受け継いできた土地だ。
加藤 向こうの森まで造園屋さんの土地で、その方から譲ってもらって建てたところなんです。園舎設計時も「できるだけこの森は残したいね」と話していて。ゼロから植えると何十年もかかるような森ですし、野田市のシンボルツリーであるけやきの木が子どもたちを見守ってくれる風景を大事にしたい、と思って設計しました。

大切なものを残しながらも、環境の変化に適応すべく、新しいものを取り入れていく。新しさのひとつは、教育目標だ。「生活を自分でつくり、明日を創れる子を育てる」と掲げ、一斉に何かをするよりも、1人ひとりが主体的に行動できることを目指している。
加藤 裸足になるかどうかも、自分で決める。気持ちいい方でどうぞ、と。あと、冬はあかぎれしてしまうので、それも伝えた上で「自分で判断しようね」とは言っています。もちろん養護の観点もあり指導もしますが、個々人が判断できる余白を残し、困ったときに保育者がフォローできるようにしておくことが大事かなと。
そう話している間にも、子どもたちはどんどん私たちのところにやってくる。「こんにちは!」とあいさつしてくれる子、「見て!」とアピールする子、少し距離を取り、でも笑みを浮かべながらこちらの様子を窺っている子。
加藤さんは「ジャズのセッションみたいに、臨機応変に子どもたちと接している」と語り始めた。
加藤 まずは、子どもたち自身がどう感じるか。例えば、チューリップに興味がある子どもがいるとします。普通だったら「みんなで育てましょう」と言って、球根を配って植えて、咲いたら終わりですよね。でも、自分ごとになっていない子もいっぱいいるわけです。「別に植えたくないし」「泥遊びしたいな」みたいな。
本来は、もっといろんな選択肢があるはずで。チューリップの花を育てたい子は、一緒に球根を買いに行って植えるのも、もちろんあり。一方で、そこには興味がなくても、ドライフラワーにして飾りたいと思う子はいるかもしれません。チューリップの花が枯れたときに、色水をつくることもできる。そうやって次々と生まれ、変化していく子どもたちの活動を、私たちは「プロジェクト」と呼んでいます。


加藤 保育者の仕事は、子どもたちの発言や興味などをもとに、活動の広がりを想定しておくことです。花がだんだん枯れてきたときには、「先生、これで色水遊びしたい」と言われてもすぐ出せるように、すりこぎを用意しておく。プロジェクトごとに選択肢をマインドマップとしてまとめながら、日々の環境づくりに頭を使っている先生もいます。
子どもも大人も、1人ひとりが尊重される場に
人には違いがある。さまざまな個性があり、やりたいことや望むことも変わりゆく。当然、プロジェクトが途中で無くなっていくことも珍しくないし、特定の活動を経験しない子どももいるが、加藤さんは「それで構わないと思う」という。
加藤 興味がないものまでみんな均等に、勉強も絵も音楽も運動も……とやらされるから、非効率になるし、“嫌い”がいっぱい生まれてくる。「そんなに無理しなくて大丈夫だよ」という思いが大前提にあります。

1人ひとりを尊重するのは、生活面でも同様だ。鼻水が出ている子どもがいる。そのときに、保育者は黙って拭いてしまうことを、しない。「拭いていい?」と一言声をかける。自分の体のことを、自分で選択できるようにする。オムツを替えるときにも、「オムツ替えていい?」。
加藤 時間になったら「全員とりあえずトイレ行くよ!」と行動させる園もあると聞きます。保育者の人手が足りない瞬間に、現場でそうせざるを得ない側面もあると思います。でも、どうでしょう。時間を分けて行う方法もあるはずです。子どもの人権も、保育者の働き方も、その両方が尊重されたほうがいいですよね。
この園は、保育者が多いほうなんです。4歳児や5歳児もいるこのテラスで、あの先生は1歳クラスの担任、あっちの先生は2歳クラス。こうして活発に遊びたい子もいれば、部屋の中で静かに過ごしたい子もいて、同じクラスだけを見ていたら難しくて。

同じ敷地内にある「野田北部幼稚園」へと、歩いて移動する。2024年春に完成した新しい園舎、今まさに建設している園舎、この夏に内装のリニューアルが予定されている園舎が立ち並ぶ。1977年に80名の園としてスタートし、現在の定員は310名。2025年度から受け入れる0・1歳児の枠を空けながら、今は2〜5歳児280名ほどが通う。
さっき通ってきた「のだのこども園」と同様に、子どもたちが思い思いにすごす園で、工事現場で働く大人たちに柵越しに話しかけている子どもたちも見える。小ぶりな容器をプールにして浸かり、どろんこになっている子どもたちもいる。

ただ、認定こども園にはなかった指定の制服やリュックが幼稚園には現状残っているなど、伝統を感じさせる面もある。残したい風習や仕組みもある一方で、子どもたちの主体性を活かした保育を幼稚園でも実践するために、変えるものは変え、これからの時代に必要な資質を育める「子ども主体の保育」により近づけようとしている過程だ。
幼稚園の部屋に、気になる構造物があった。保育環境の専門家を交えながら、なんと保護者のみなさんとつくったそうだ。
加藤 子どもたちが室内で多様な遊びを展開するために、平面ではなく立体で環境を構成する必要があって。この櫓の一番高いところにも、登れる子もいますよ。ここに大人がその子の姿を無視して乗せてしまうと、登る筋力が発達していないので降りられず怪我をしてしまいます。子どもたちそれぞれに、自分で登れる範囲がある。それに合わせて遊んでいます。

加藤 この遊具は、あえて保護者の方と一緒につくったんです。私たちは園のしおりに“「おたがいさま」で育ちます”と書いています。保育者が最大限に配慮していても、子どもたちが一緒に過ごしていたら多少は怪我をするし、喧嘩もする。そんなとき、園や保育者が「サービスを提供する側」としか見られていないと、クレームを言うだけの対象になります。
でも、この遊具づくりのような機会があれば、保護者にとっても愛着が湧く。それぞれが当事者になれることを増やしながら、普段から顔見知りになっていくと、何かあった際にも、遊具や保育への理解をしていただきやすくなると思っています。それが結果的に、子どもたちにとっての豊かな環境づくりにつながるのかなと。
「点」から「面」での社会提案のフェーズへ
TSUTAYAなどを運営する〈カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社〉に勤務後、2012年に父が経営する〈加藤学園〉へ入職した加藤さん。戻って3年目となる2015年に、実は大きな決断をしていた。単体で400人近くに膨れ上がっていた幼稚園の園児数を減らしたのだ。
加藤 シンプルに子どもが増えていった昭和と平成を突き抜けて、私が来たときには、多い学年で140人もいました。1クラス35人を、1人の担任の先生が見ていた時代です。
また当時は、マーチングバンドにも力を入れていました。6月、7月、そして夏休みを終えて9月と、園庭で大きな太鼓を持って練習していて。先生たちは声を枯らし、一生懸命に指導をしてくれていました。頑張りの成果を最後に披露すると、その姿に心を動かされるのですが……。
つらい経験、我慢する経験も時には大事だとは思います。けれど、この乳幼児期に、子どもたちの意志を超えて、みんなで一斉に同じことを3カ月もやる必要があるのかな、と疑問に感じました。そこで保護者のみなさんに「行事を変えていきたい」「小集団で、もっと丁寧に見て育てていきたい」と伝え、まずは1学年を100人にしたんです。お断りしたご家庭には大変ご迷惑をお掛けしましたが、一方で先生の数は1.5倍にし、幼稚園に2歳児クラスや未就園児のクラスも新設して、4年間通えるようにしました。

伝統を変えていくにあたっては、週1回メールマガジンも配信した。「子どもは行事だけで育つわけではありません」「まず保護者の方が笑って過ごせるようにしましょう」「お父さんは、お母さんだけに子育てを任せていたら厳しいですよ」と、現代の保育にまつわるいろいろな価値観を言葉にしていった。メールマガジンの執筆には、毎週10時間ほどかけていたそうだ。さらに、保育者が写真を撮れるカメラを1人1台ずつ購入して、保育の見える化を地道に進めていった。
2017年に法人の理事長を引き継いだ加藤さんはさらに改革を進める。2018年には流山市に定員80名の「Kanade流山セントラルパーク保育園」、翌年に「のだのこども園」を開園し、乳児を受け入れ始めた。
加藤さんは、“DIY”で考え、つくっていく人だ。実家の幼稚園に戻り、一斉保育や行事に違和感を抱いて手を入れながら、「学校法人が乳児保育をやらない理由はない」と考えるようになっていた。
加藤 学校法人は、社会に対して、教育の質を保つことが求められていると思っています。子どもをお預かりする法人としてそこに向き合ったとき、乳児もその対象にするべきだと思いましたし、「私たちも保育園をやったらこれだけできる」と示したい気持ちもあった。待機児童対策の中でご縁をいただいた面もありましたが、量の補充のためではなくて、保育の質を提案していきたいと考えていました。

子どもたちにとって無理のある行事を設けず、暮らしの中で生まれる活動を軸にした「Kanade流山セントラルパーク保育園」と「のだのこども園」では、加藤さんが目指す子ども主体の保育をある程度提示することができた。ただ、ひとつひとつの園が単独で成長し、現状では園同士が積極的に交われてはいない。
また歴史ある「野田北部幼稚園」も、残したい伝統がある一方で、これからの乳幼児教育に則した園生活にするために変えていかなければならない部分もあった。さらには、園に在籍していなくても子どもと保護者が利用できる子育て支援機能も増やしている最中だ。取材当日にも、多くの子どもたちとその保護者が集い、笑顔で交流する姿が見られた。新園舎が完成したら、以前からの幼稚園の建物には、障害のある子どものための児童発達支援事業所もオープンする。
名前もバラバラ、つくられたプロセスもバラバラ。しかし、運営する法人は同じで、保育・教育をするときに根っこにある部分も同じだ。加藤さんは、複数施設の体制を6〜7年続けてきて、法人全体で向かう方向を明確にする必要があると感じた。
加藤 これからは、地域を支える多機能の集合体になりたい。「点」から「面」になって、小学生以上の子ども、そして大人、近隣のおじいちゃん・おばあちゃんも含めた人たちのハブになっていきたい。そのときに、より多様で、魅力的なスタッフと高度化した組織が必要になると感じました。
そうして、リブランディングのプロジェクトが始まった。

デザイナー小田雄太さんとの共創から浮かびあがる、目指す法人の姿
リブランディングのパートナーとなった〈COMPOUND〉の小田さんと加藤さんの出会いは、個性豊かな飲食店や物販店が集まる下北沢の商業施設「BONUS TRACK」がオープンした2020年にまで遡る。
加藤 「BONUS TRACK」に行ったら、おしゃれな建物にだるまのイラストが光ってるわけですよ(笑)。これはなんだろう、と思って、そのロゴマークをデザインした小田さんに連絡したのが最初でした。
小田 あそこは、施設の隣に保育園があります。その保育園側にも大きなサインを出す必要があるけれど、駅側のような煌々とした内照式のデザインにはしたくなくて。そこで、全部細かいタイルでつくったんですよ。だるまの胴体部分の縞々などの特殊な形のタイルは陶芸家の方にわざわざお願いするなど、園の子どもたちにとって親しみをもってもらいたいなと目立たないところまでこだわってつくりました。それを加藤さんがちゃんと見てくださっていたんです。

他にも、加藤さんが持っていた50個限定の波佐見焼の陶器を、仕事として関わっていた小田さんも持っているなどセレンディピティがあった。聞いてきた音楽、読んできた本なども含め、大量にある引き出しから、求めたら出してくれるイメージが加藤さんの中で湧いてきた。
歴史のある幼稚園に、外部からデザイナーを入れる。まずその選択に、加藤さんの意志が詰まっていた。
加藤 2025年春に、「野田北部幼稚園」も認定こども園になります。そのタイミングで、法人名を変えて3つの園名とロゴも統一したいと考えました。
学校法人は、一般的なイメージが“守り”ですよね。私自身も、名前や園に愛着を持っていて、手放すのは心苦しい気持ちがあります。でも、地域を「面」で支えられる存在になるためには、大事なものは守りつつ、次のステップに進んでいかなければならない。デザイナーさんに求めていたのは、「どのようにビジョンを斜めに飛ばしてくださるか」でした。

加藤さんが望んだのは、新法人のロゴデザインだけではない。「最後の表面的なものを整えるだけではなく、『なぜそのようにやっているのか』を考えてもらう」という仕事のスタイルを取る小田さんと議論を積み重ね、経営における課題を整理していった。その過程では、例えば「組織のあり方」のような具体的な問題も浮かび上がった。
小田 これまでの加藤さんは、全体の経営から現場レベルまで全てを見られてきた方でした。ただ、お話ししていくなかで、「経営者として現場に身を置きつつも、そこに拘泥するのではなく、より上位の概念を新しくつくり出そうと頑張っている方なんだな」と感じました。私はクリエイティブパートナーとしてさまざまな経営者の方と向き合ってきましたが、経営者はやっぱり経営のことを考えなきゃいけないし、組織を具体的な形で発展させていくことを考えなきゃいけないと捉えています。
そこで、プロジェクトを始める上で今の体制がどうなっているのかヒアリングしながら、「加藤さんがやろうとしていることをやるとしたら、組織図はこうなりますよね」と提案させてもらいました。リブランディングを進めるときには、組織としてどうなっていくのを目指すのかがすごく重要だからです。組織実態とかけ離れたリブランディングやデザインほど無意味なものはありません。

加藤さんは「小田さんと出会うまで、組織図をつくり直すなんて一度も考えたことがなかったです」と振り返る。
加藤 多くの学校法人は、ひとつの園をひとつの法人で運営しています。だから、理事長と園長が同じ場合も珍しくない。でも、私たちがやる教育・保育は、幼稚園、保育園、認定こども園だけでなく、子育て支援、障害福祉、さらに今後は学齢期の支援など、機能が複雑化していく。経営として採算やスタッフィングなどを見る役割と、現場で中身をつくっていく役割を両立するのは無理だと気付かされたんです。
小田 議論していくなかで、加藤さんは、経営的な視点、教育・保育的な視点、個人的な視点の3つを、ニュートラルにバランスよく持っている方なんだと気づいていきました。ちゃんと個人の考え方や感性、欲望を持ちながら、教育・保育の質にも、全体の経営にもコミットしている。
そんな加藤さんが、園舎の建て替えだけでなく、法人そのものをリブランディングしていくのは、かなり勇気がいることをやろうとしているんだなと。こうしたとき、経営者は1人でいろいろ決めていかなければなりません。そこに関しては、言語化や意思決定をサポートする存在が必要なんだろうな、とは考えていましたね。

加藤さんが実現したかったイメージを園舎の設計士の方も交え辿っていくと、「公園」という言葉が浮かんできた。パブリックな場所に、楽しみ方の違う人が混在していて、好きなことをして過ごしている。犬の散歩をしている人たちは、互いに挨拶をする。ゆるやかな繋がりがある、心地いい空間。
「村」という表現も、加藤さんは好んで用いる。例えば「野田北部幼稚園」の園舎は、全部で5棟。大きな箱でどっしりと構えるのではなく、小さな棟が村のように繋がっている。それは「のだのこども園」にある軒の深さにも象徴されていて、中間領域が豊かに用意され、シームレスに結びつく。
「公園」や「村」のモチーフは、敷地内の園庭環境や、園舎の建て方に限った話ではない。1人ひとりが自己決定できていること、「おたがいさま」であること、権利が守られていること、「点」から「面」にしていくこと──。加藤さんは「公園」や「村」を実に多角的に捉えている。そういう風景を“絶景”と表現し、「それが実現できたら、法人として存在意義がある」と考えていた。

新名称は「thanka」、ステートメントは「手を繋ぎにいく」
新しい法人名は「thanka」に決まった。読み方は「さんか」。そこには次のような3つの意味がある。
- 燦花:燦々と輝く太陽のもとで沢山の花が咲くように、子どもたちの笑顔あふれる社会を創造するためにわたしたちは存在します。
- 讃歌:それは、園に集う子どもと大人が、歌を歌うように、その人なりの人生を謳歌してほしいという願いが込められています。
- 参加:こどもたちが社会の構成員(一市民)として尊重され社会参加できている世界を実現したい。そのために、わたしたちの園運営には、ひとつの村のように、園の垣根を超えて多くの大人が参加し、子ども文化を創造する園をつくりたい。
英語表記の「THANK – A」には「感謝をする」という意味も込められている。加藤さんが数えきれないほどの名称候補を出し、絞った数案を携えて園長先生らとワークショップをした。最後は、加藤さんが責任を持って決めた言葉だ。
加藤 私がコピーライターを入れて助けを請おうとしていたのを、小田さんから「いや、加藤さんなら出せますから」と言われ続けて。部活の顧問みたいに傍で鍛えられました(笑)。
小田 「いやいや、まだいけますよ」と(笑)。加藤さんの文化背景やニュートラルな考え方、多様な視点を持っているところを感じて、言葉を出せる人だと確信していたんです。それに今回求められるのは、加藤さんにとっても挑戦的な取り組みの真ん中に位置するような言葉です。別の人から借り物のように持ってきてしまえば早いのかもしれませんが、それだと近い将来、何かにつまづいたときに立ち戻れるステートメントにはならないのではと考えていました。
法人名にあわせ、3つの園名は「thanka幼稚園・保育園 のだほくぶ」「thankaこども園 のだ」「thankaこども園 ながれやま」として統一していく。
一方で、法人のミッションステートメントは「手を繋ぎにいく」となった。ここに、主語はあえて入れていない。子ども、保育者、保護者、地域の人、あるいはその他の誰か。それぞれが、それぞれに助けの手を差し伸べたり、遊びに誘い出したりしていく。そんなメッセージが込められた。
このステートメントと「thanka」の名称にあわせ、小田さんはデザイナーとして法人と園のサインを手掛ける。生まれたのは、「手」という漢字の象形文字を用いて、同心円上の構造の中に入れたロゴ。3つの「手」は繋がった状態ではない。一対一でもない。異なる主体が混ざり合って、今まさに“繋ごうとしている”。

「手を繋ぎにいく」の言葉はシンプルだが深い。実は小田さんが提案したロゴデザインには、ボツとなった案があった。
加藤 めちゃくちゃ悩んだんですよ(笑)。私みたいにデザインのことをわかっていない人間が、実績のある小田さんにNOを言うのって、なかなかヘビーですよね……。でも、何かが違うと思ったのは事実で、そのNOを伝えるために小田さんに何と言うか考えるところが、良い言語化になりました。
小田さんの最初の提案は、土から芽が出ているような部分と、手が出ている部分があって、安定感や誠実さ、学校法人としての“守り”のニュアンスがあったんです。私たちは誠実さをベースにして運営しているので、それは正しいんですよ。
でも、私たちがこれから目指す学校法人のあり方は“守り”だけではない、とそのときに気づきました。ひとつの園で安定して完結するのではなくて、同心円状に関係者を増やしていきたいし、保育者の価値観をアップデートしていきたい。だから「もうちょっと駆動感が欲しい」という、曖昧なリクエストをして返しました。
小田 少しニュアンスが違うと言われて、「そのニュアンスの中にある言葉を探っていきませんか?」みたいなやり取りをさせてもらって。最初の案も自分の中では相当突き詰めて出した一案だったんですけど、そうやって加藤さんと議論を重ねていくと、やっぱりまだ「手を繋ぎにいく」の理解が足りなかったなと気づいたんです。その言葉が持っている可能性、繋がる前の未決定な部分を、知恵熱が出るほど考えて、もう一度デザインに落とし込みました。
2人がつくりあげたステートメントとロゴには、園児たちだけでなく、子どもを取り巻く大人たちへのまなざしも強く反映されている。特に加藤さんは「園の運営は、先生たちありき」と強調する。ただ、保育士や幼稚園教諭の労働環境は業界として課題が多い。加えて、「外部との交流を持ちづらいこと」にも加藤さんは触れる。

加藤 保育者は、家と保育園を往復してずっと子どもを見ていたら、毎日が終わっていってしまう。そうなると、価値観が広がらないじゃないですか。そこは、一般企業から転職してくると、シンプルに「多様性がないな」と感じてしまいました。習慣や経験にも幅を持っていてほしいし、そうした機会を提供したいと思っています。生活に幅があるからこそ、子どもからのアクションに応答するジャズの力、瞬発力が生まれる。大学までに座学で学んだ知識で抽象的に考えることも大事ですが、子どもたちは具体のところで生きているので、そこを耕していく必要があります。
だから5年、10年単位で考えると、まずは保育者が学んでいける環境を整理していきたい。教育・保育に携わる1人ひとりの思いがあってこそ運営できるのだから、先生たちがワクワクすることのできる法人でありたいし、その旗印となるようなロゴであってほしかったんです。
加藤さんは、保育者たちの副業を可能にしたいと語る。例えば、食育に興味のある人なら、外部で食のワークショップをやってみる。もし個人で取り組むのが大変なら、〈thanka〉が受け皿となり、保育者たちが副業をするためのプラットフォームとして別会社を立ち上げてもいいという。
外に出ることで、行った先で出会いが生まれる。その出会いの経験が、保育者の学び、多様なキャリアとなり、子どもに返ってくるのが理想だ。
加藤 3世代世帯がいなくなっていき、地域の繋がりも希薄になっていっています。かと言って、園や学校が学びの機能を全部補完することは難しい。そうした中で、多様な出来事が当たり前のようにたくさん起こっていくのが、〈thanka〉らしい雰囲気なんだろうなと思っています。いろんな人を混ぜ込んでいく、そんな場を僕はつくっていきたいんです。

保護者も地域も混ぜ込んでいく
混ぜ込んでいく──。これは〈thanka〉を表現する上で欠かせないキーワードだ。
多様な人が手を繋ぎにいける場をつくり出すことこそ、法人の使命だと加藤さんは考えている。
加藤 今の時代、生活に余裕のある家庭もあれば、本当に過酷な家庭もあって、子ども時代の経験値の差がすごく大きくなっているんです。子どもたちを預かっていると、それはもう如実に感じます。じゃあそこで、最終的にその子たちが大人になったときに社会でわかり合えるかどうかを考えたとき、私たちのような地場の事業者がいろんな人たちを混ぜ込んでいかないと、ちょっと厳しいのではないかな、と。
だからこそ、加藤さんは保護者がどんどん参加できるようにする。それも、強制はしない。「参加したい」と思えるアクティビティに参加してもらえればいい。保護者が漫画を持ち寄って、ただ読むだけの会も開いた。別の保護者が隣で漫画を読んでいたら、どうしても気になって、話しかけてしまう。そこで、出会いが生まれる。「バーベキューをするだけでもいい」と加藤さんは言う。
ポイントは、保育者たちが準備をしすぎないこと。「お客様」ではなくて「おたがいさま」のコミュニティとして、当事者になってもらう。そもそも、企画の発起人になってもらうところから始めることも少なくない。
加藤 混ざることが重要なのは、保護者だけじゃなく、地域の方も同じなんです。近隣から「騒音」とクレームを入れられている保育園でも、園内で育てたお米を「できたよー!」と日頃から持って行っていたら、「騒音」にならないと思うんですよ。私たちがやることは、地場に根を張って、まず隣のお宅に挨拶に行くこと。昔の幼稚園が当たり前にやってたことを、いろんなところでやっていく……それだけのことが実は大事だとなんとなく見えてきたのが、この6年ほどの学びだと思っています。

これまで続けてきたことを、これからも続けていく。今回のリブランディングは、自分たちが続けてきたことの価値を、再確認する作業にもなった。
加藤 リブランディングで新しい法人名が出来て、新しい服に着せ替えるようなイメージを、最初は持っていたんです。でも、やってみたら違っていました。もともと個性のある3つの園が先にできていたけれども、根っこの部分は一緒だよね、と。だから、今すでにやっていることに対して、ちゃんと背中を押してあげるという感覚が強いです。
統一された園名の中でもっと交流し合ったり、法人の単位で地域から受け取ったものを、各園のみんなに還元したり。保育者のキャリアについても、上から与えるのは〈thanka〉らしくないので、例えばスポーツが好きな人同士で、一緒にスポーツの活動を考えてみる。そこに、地域の方を巻き込んでほしいなと思います。
直近では、早朝に地元の農家さんの畑に集まって「採れたてのとうもろこしを楽しむ会」をやります。もちろん希望制で、参加したい人だけ。とうもろこしを収穫して、その場で食べると、めちゃくちゃ美味しいんですよ。

加藤 大事なのは、この農家の瀬能さんはずっと園に来てくれているってことなんです。子どもが何か育てたいと思ったときに、保育者ではわからないので、こういう地域の方に声をかけて、来て教えてもらう。その体験を重ねながら、保育者も子どもたちも、自ら学んでいく方法を身につけていくんですね。
そうやって何回もプロジェクトをご一緒するうちに、瀬能さんは「畑の神様」みたいな存在になりました(笑)。子どもたちも「神様、次はいつ来る?」って聞いて、みんなで絵を描いたりして、また別のプロジェクトを始めていく。私の役割は、そんな風にこれまでもやってきたことに補助線を引きながら、学びの意識づけをすることなのかな、と思っています。
インタビューが終わり、リラックスした加藤さんが「これ、もう雑談ですけど」と語り始めた。「誰でも入れるバスケットコートを敷地内にポンとつくるのが、一番コミュニティとしての効果があるなと思って」。
すかさず小田さんが「バスケ教えてるんで、いつでも来ますよ」と応じる。「クライアント」と「デザイナー」の関係から、「バスケを一緒にやる仲間」へ、すでに混ぜ込まれている。加藤さんにとって、一緒に“DIY”をしていくのが基本的な考え方なのだろう。かつて室内遊具を保護者とつくったように、一緒に関わるから愛着が湧くし、ともに当事者になれる。
加藤さんは、発達障害の傾向があるお子さんと保護者の面談を、年間30組ほどのペースで続けてきたそうだ。自身の子育てで苦労してきた経験も明かしつつ、ここに通う親子に必要だから、と児童発達支援事業所を設置する。卒園生たちの居場所が少ないことも、加藤さんは課題に思っている。必要だから、建設中の新棟に小学生たちのアフタースクールを設置することも検討している。子ども以上に保護者の支援が重要となるケースも多い。産後うつを防ぐためにも、ちょっと顔を出せる子育て広場が必要だから、つくった。
そうやってここに根を張る学校法人が、今まで以上にいろんな場所を持ち、地域全体を支える存在になっていく。加藤さんの願いが形になれば、いつか〈thanka〉のバスケコートで、老若男女、障害のある人もない人も混ぜ込まれて、ボールを繋いでいる“絶景”が見られるかもしれない。

Profile
Profile
![]()
-
小田雄太
COMPOUND inc. 代表
デザイナー/アートディレクター。2004年多摩美術大学GD学科卒業後、アートユニット明和電機 宣伝部、デザイン会社数社を経て2011年にCOMPOUNDinc.設立。2020年に文化庁メディア芸術広報事業クリエイティブディレクター就任。多摩美術大学GD科・日本芸術大学A&A教員。
平面デザインを軸足にファッション、アート、メディア、まちづくりやエリアデザインの事業開発とリードデザインを手がける。最近の主な仕事は、ニュースメディア「NewsPicks」創業リードデザイン(2015)、下北沢エリア開発「BONUSTRACK」VI・サイン計画(2020)、渋谷インキュベーションセンター「100BANCH」VI・サイン計画(2017)、富士吉田市アートプロジェクト「Fuji Textile Week」プランニング・VI計画(2021)、ANB Tokyo「END展」プランニング・VI計画(2021)、山梨県立美術館メタバース事業「LABONCHI」プロデュース・VI計画(2023)、COMME des GARÇONS「noir kei ninomiya」デザインワーク(2014-2021)、文化庁メディア芸術広報事業クリエイティブディレクター(2020-)、ICCキッズプログラム『キミ(). コード().セカイ().』展覧会グラフィック(2024)
- ライター:遠藤光太
-
フリーライター。発達障害(ASD・ADHD)の当事者。興味のある分野は、社会的マイノリティ、福祉、表現、コミュニティ、スポーツなど。初単著に『僕は死なない子育てをする』(創元社)。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事
vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」